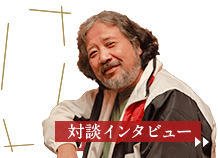今年も彼岸花は咲き乱れる。紅く紅く。見慣れた風景に夏の終わりを告げ、風の心地よさを改めて気づかせる。今年の夏は暑かった。その夏も終わり、また秋が訪れ、そして冬に。去年と変わらない冬。一人の女性が記憶の中にしかいないこと以外。変わらない季節が訪れる。

彼岸花を目の当たりにすると、ノスタルジックに。
流石に都市部で彼岸花を目のあたりにすることはない。やはり緑が多い町並みに現れる。田んぼ畑の字道であり、道端の路肩であり。そしてその群生によるいつもの光景への紅い専有比の高さと、普段の日常とは異なる色合いに、自然とやはり目を奪われるのである。そして時期はお彼岸。当然ながらその光景は、亡き人たちの記憶が思い出される。もう全然大人なのに。思い出される記憶は、幼き頃のものが彼岸花に負けないくらい鮮明によみがえる。色味はセピアでコントラストは強めに。

八女のまつり「あかりとちゃっぽんぽん」
時を同じく、今年は八女のまつり、あかりとちゃっぽんぽんに携わっていた。八女福島、この季節の風物詩である燈籠人形と、その街並みを、提灯と竹灯籠で夜の町並みを照らしていた祭りである。慌ただしい運営の中、ふと目を奪われる。小さい子供とその祖父母が、燈籠人形を観ている。街並みを溢れんばかりの喜怒哀楽を用いて歩いている。その姿にかつての自分を重ねたり、提灯のあかりと竹灯籠のあかりが照らす薄明かりが回想に拍車をかけていた。

記憶がない彼女と記憶がある自分。
認知症であった彼女がなくなったのは今年の春。完全に忘れさられた自分と昔の姿を忘れられないでいた自分。人間は勝手な生き物だ。事実を認められず、その現実に目を背けてばかりいた。生きているうちにできたことはたくさんあっただろうに。この10年位の思い出はほぼない。同じ人なのに。同じ思いを持っているはずなのに。その現実が思い出になっただろうに。避けて生きることしかできていなかった。

いなくなった人と今いる自分。
結局最期は仕事で看取ることもなく、葬式も出ることができず。あれから半年近く経ち、慌ただしく過ごしている。そして、彼岸花と提灯と竹あかり。照らしたものと染まったものの先にあったものは。弱い自分とセピア色の思い出。天寿を全うした彼女の大往生を素直に見送れない罪悪感と、昔の思い出しか話せない疎外感。

一生一緒にいることなんてない。
これからも先に死にゆく人もいるだろう。また途中で記憶をなくし、生きながらも描いていた人じゃなくなることもあるだろう。ただ、一生一緒にいるなんてことはない。人間誰しも最期はひとり。ひとりを見送るその日まで。これまで受けた恩恵に応えていくことが恩返し。彼岸花を見てセピア色ではない鮮明なビビッドな思い出を思い返せるその日まで。いつしかそんな想いで彼岸花を眺めてみたい。