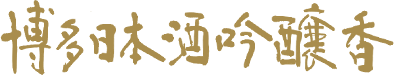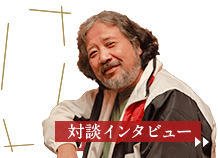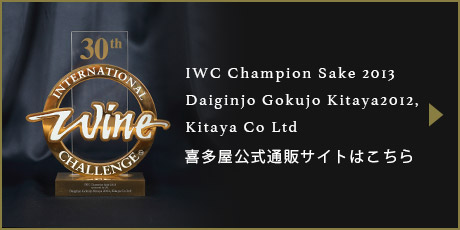熟成酒の独楽蔵が面白い

「杜の蔵(もりのくら)」(久留米市三潴町)に、福岡市中央区の酒屋「友添本店」の友添健二さん(写真左)と訪問した。
良い意味で“極端”な酒蔵だと思った。
2005年に九州で初めて純米酒だけを造る蔵になったのは、酒の関係者では有名な話。
一般的に日本酒には味などを整えるために、醸造アルコールを添加する。
いわゆる「アル添」をしない清酒にこだわった杜の蔵では今、フレッシュな酒と数年熟成させた酒という、両極端な2本の柱がある。
その中で熟成酒の「独楽蔵」シリーズをつくり上げたストーリーを紹介したい。
昭和16年製造の酒に「独楽蔵」のヒントを得る

酒のディスカウント店が全国各地に進出していた1990年代。
価格競争で大手酒蔵に劣勢な地方の小中規模の造り酒屋が、生き残り先を模索していたとき、杜の蔵が考えたのが熟成酒造りだった。
日本酒の世界では「古酒」と言われるジャンルである。
ヒントは、屋根裏から見つかった昭和16年に製造された日本酒。
「泥水のような色をしていたんですけど、見た目と違って味に透き通った感があり、お酒の力強さも感じられたんです」と、5代目の社長、森永一弘さんは言う。
心震わす熟成酒の独楽蔵

蔵元の子として生まれながら、「酒が大嫌いだった」という森永さん(写真左)。
東京の大手デパートでサラリーマン生活を送り、故郷の三潴に戻ってきて2年ぐらい経った時のことだ。
「独楽蔵」をやっていこうと強く思う出来事があった。
寒い日だった。
仕事から家に戻り、まだ暖まってない部屋で、日本酒をぬる燗にした。
口に含み、クイッと顔を上に上げると、冷え切った体の中を温かいものが流れていく。
「うまい!」と思うのと同時に、ブルッと体が震えた。
体だけでなく、「心も震えたんですよね」と森永社長。
「日本酒って、これだよね。この感動のために、お酒造りをやりたいなあと思ったんです」
独楽蔵のテーマは「ゆっくりとじっくりと」

肉に油物にスパイスたっぷりの料理。
日本人の変わりゆく食生活に無理なく合わせられる日本酒として、改良を加えていった。
5代目自らの晩酌で実験を繰り返したのが今の「独楽蔵」だ。
テーマは「ゆっくりとじっくりと」。
酒造りもそうだが、食とお酒を楽しむ時間もゆっくりとじっくりと。
そして、「独楽蔵」は冷やよりも、ぬるめがいい。
寒い時期に、身も心も温めてくれる日本酒である。
友添健二さんの福岡の日本酒紹介サイト、大吟醸で大往生で杜の蔵の話題やお酒購入ができます(近日公開予定)。